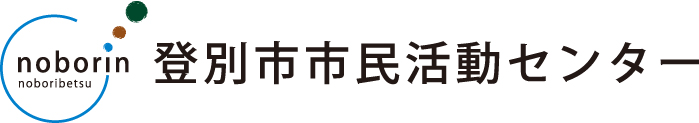『東京大学社会教育学研究室公開講座』受講第3回目




2023.2.13 19:00~21:00
1階サロンスペースにて東京大学社会教育学研究室公開講座「社会教育の再設計」第3回目をサテライト型聴講モデルとしてのぼりんで受講しました。
今回は「行政依存が社会を壊す」というテーマで対談が始まりました。
本来自治活動の場である「公民館」が地域づくりセンターや活動センターという名称に変わったことに端を発して、本来掲げてきた「公民館」の機能が「行政がやっているサービス」と捉えられてしまいがちになっているのでは、という問題提起に始まりました。
- 名称の問題でしょうか?
地域のつながりで見守り関わってきたきたような課題に対して、補助金などを使って事業として取り組むケースが、補助がなくなり一過性の取り組みとなってしまい、なおかつ、これまで地域にあった繋がりや見守りも失われてしまって悪循環に陥ってしまうという本末転倒なことが起きていると鋭く指摘します。
- 私たちの意識はどうあればいいのか。
- これらはどうして起こってしまうのか。
さまざまな事例があげられ、その要因を探るべく放談として続きます。
戦後、工業社会になり農民が都市へ移住し大量の孤独な労働者が出来たはいいが地元への愛着も薄れ自分の生活だけを考えるようになってしまった。社会を考えることがなくなってしまったのではないか。「自分の生活と社会と切れちゃう(のが都市化であり)、そしてそれをつなぐのが市場」。つまり、孤独を商品やお金で埋め合わせている状態が生まれる。社会の当事者ということを見失っていく中で、「自治」に関わる「自治体」が、「行政体」になってしまったのではないかと言います。
-「行政依存」という問題はなぜ起こるのだろうか。
個人の意識の問題ではなく社会の構造としてそういう課題が生まれたのではないか、考察が続きます。行政という仕組みはよりよい社会づくりに向けての管理の仕組みであって、自治があって機能しているものなのに…、そのような問いかけが続きます。
最後に牧野教授が作成された文章「自己を社会的存在として意識し、位置づける方策が必要となる。自他の相互承認と相互扶助を可能とする”場所の基礎となるべきもの”が問われなければならない。(~第5期中央教育審議会生涯学習分科会における検討状況~(1)より)」という文章の紹介がありました。まさに今住民同士の「絆」という場所の基礎なるものが強化されないといけない時であるのではとまとめられディープな会が終了しました。
今回のぼりんのこの講座に参加された方からの感想で、イベントをたくさん実施している方が自分がなんの為にイベントをやるのかというと、お祭りなんかのイベントをやると人の組織や繋がりが出来てそれが災害が起こった時に非常に機能するとの貴重なご意見も頂きました。
次回は2/20(月)19:00~21:00 第4回目「孤立は自立ではない」というテーマです。